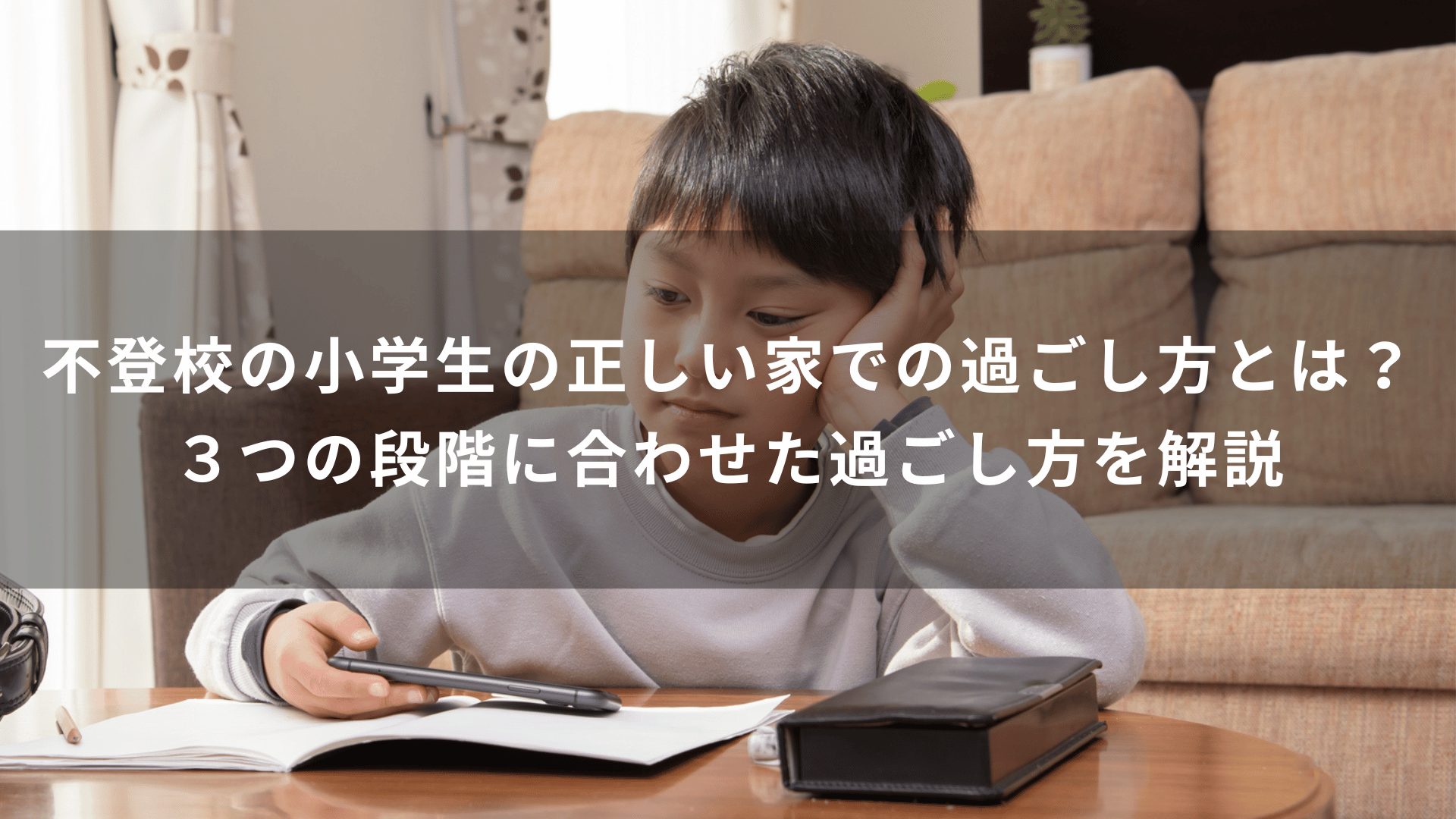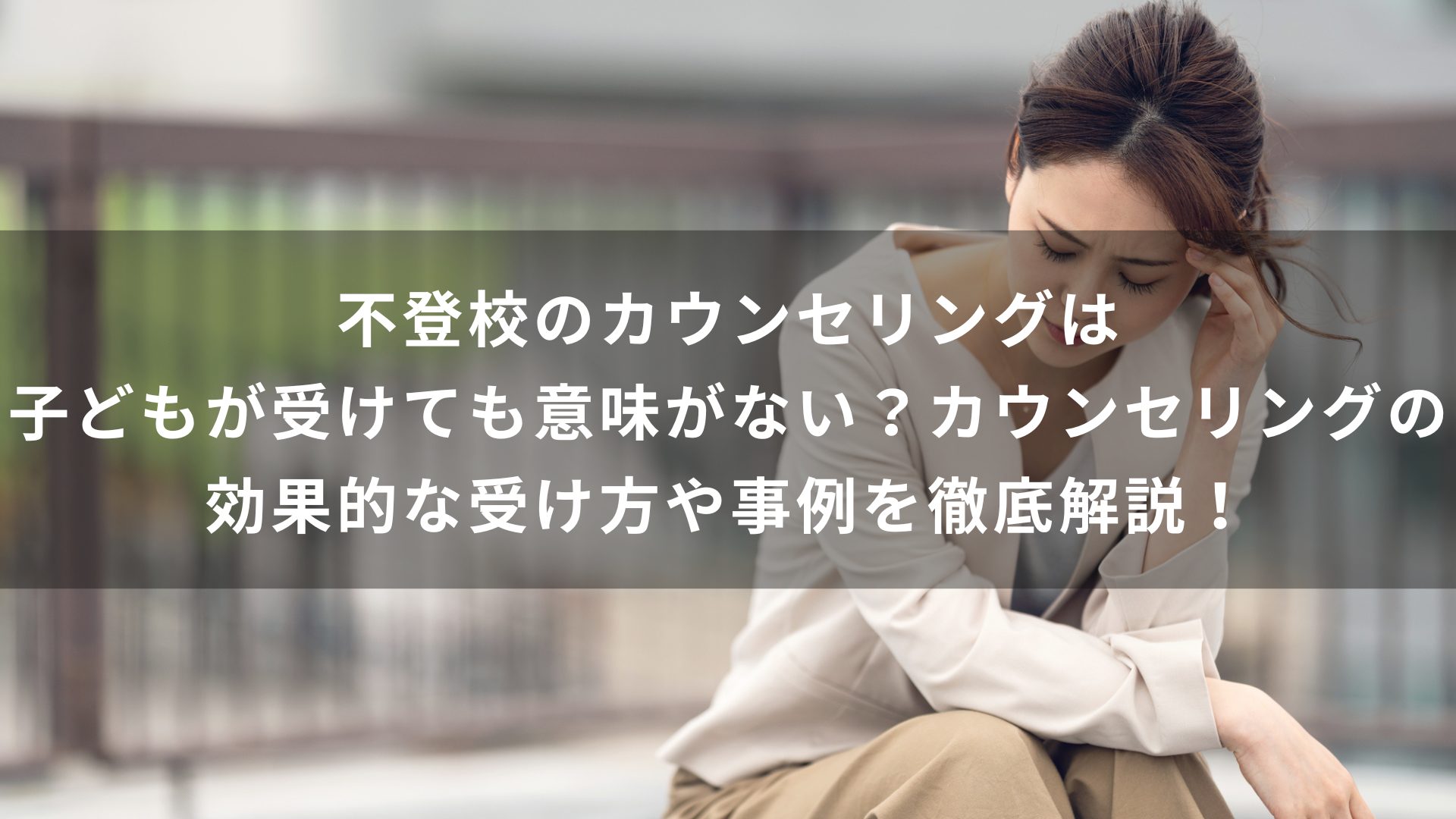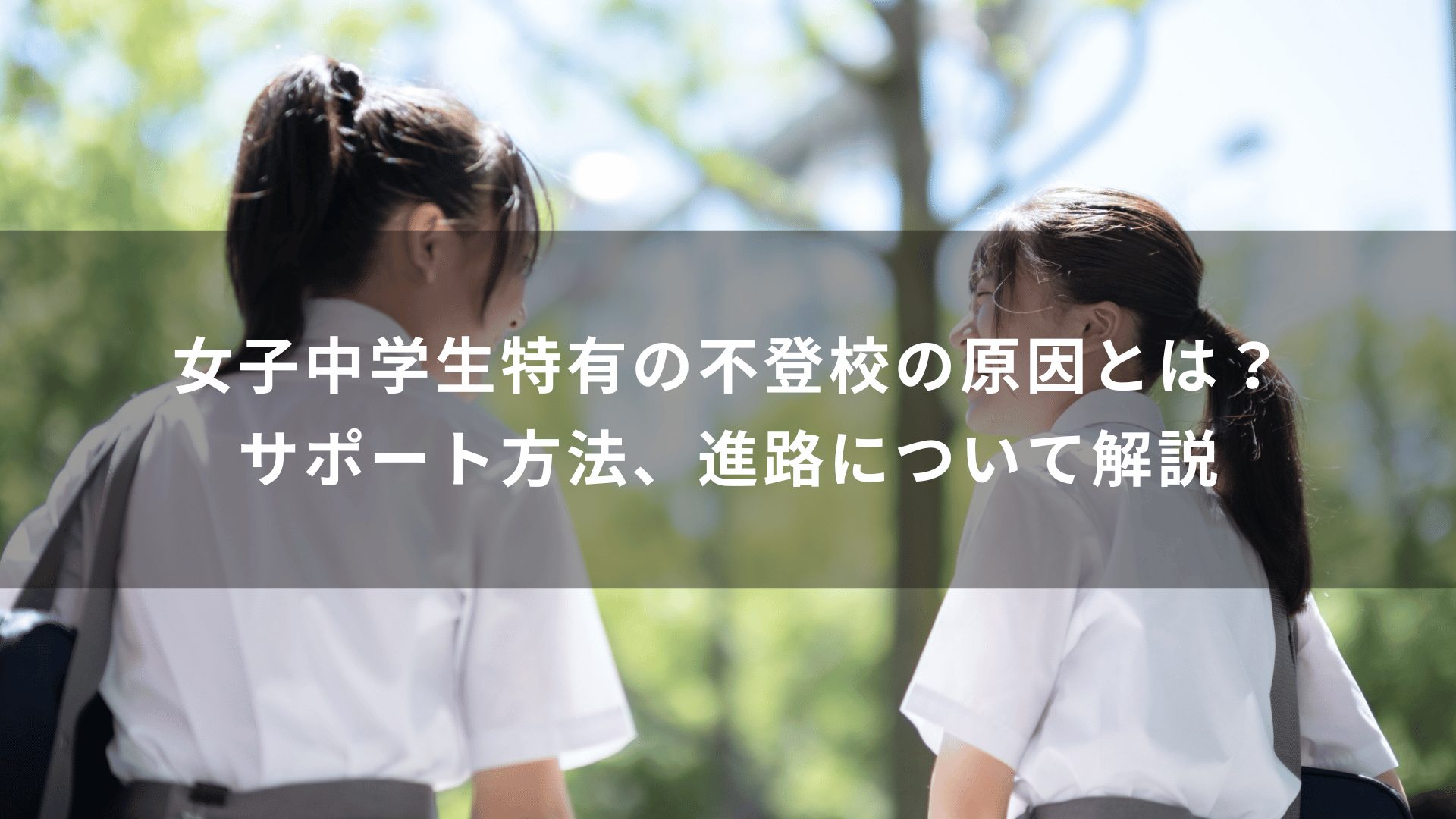小学生の子どもが不登校になると、家でどのように過ごさせたらいいのか気になるかと思います。今まで学校に通っていた時間は勉強をさせたほうがいい?動画やYouTubeばかりでダラダラすごして大丈夫?などと不安に思っている保護者も多いかと思います。
家での過ごし方によって元気を取り戻し、いきいきと生活を送れるようになることもあれば、ズルズルと不登校が続き、引きこもりになることもあります。特に小学生の不登校は長期化しやすいといわれていて、家での過ごし方がとても大切です。
では、不登校の小学生はどのように家で過ごすと良いのでしょうか。不登校になってから回復するまでの段階とともに、その特徴と正しい家での過ごし方について詳しく解説します。
不登校の段階によって正しい家での過ごし方は違う

不登校になってから回復するまでには、初期段階・中期段階・後期段階の3つの段階があります。それぞれの時期によって子どもの心身の状態が異なり、その時期に合わせた過ごし方をすることが大切です。
例えば、不登校の初期段階は、心と体が疲弊しきった状態です。この時期に、「学校を休んでいるなら勉強しなさい」と言われても、子どもはがんばるエネルギーがありません。それだけでなく、保護者に対して心を閉ざしてしまい、回復が遅れてしまう場合もあります。
段階に合わせて過ごし方を変えることで少しずつエネルギーが溜まり、中期段階、後期段階と次の一歩に向けた動きが取れるようになります。
【不登校初期段階】特徴と正しい家での過ごし方

「不登校」という行動に至る前から、子どもは何らかのストレスや精神的な不安を抱え、それがピークを迎えたことで不登校という行動が現れます。この時期の子どもに必要な事は、心と体をゆっくり休ませることです。次の段階に進むために、必要なエネルギーを溜めるイメージで過ごしましょう。
以下では、小学生が家で過ごす時に気を付けたいポイントと、正しい家での過ごし方について詳しく解説していきます。
●学校に行きなさいと言わない
●家での過ごし方を強要しない
●感情的になりすぎない
●過干渉にならない
●突き放すような言動をしない
●しっかりと休ませる
●好きなことをさせる
●生活習慣をつける
●コミュニケーションをとる
この時期に無理やり学校に行かせたり、無理やり勉強をさせようとしたりすることは厳禁です。
ゲームやYouTubeなど、好きなことばかりしている姿を見ると、甘やかしているような気持ちになり、「やめさせたほうがいいかな」「元気なら学校に行かせようかな」「勉強させようかな」と思うかもしれません。
ですが、好きな事に熱中する理由には、「不安に向き合いたくない」「現実逃避」「ゲームの中の世界が居場所になる」という気持ちが隠れているかもしれません。好きなことをして明るい気分になる時間も大切だと考えましょう。
ただし、無制限に好きなことをさせてしまうと生活リズムの乱れやゲーム依存などの恐れもあります。大人でも一度生活リズムが乱れると立て直すことは難しいものです。
保護者は子どもの気持ちを尊重しつつ、「遊びのルールを決める」、「決まった時間に子どもを起こす」、「決まった時間に食事をとる」など、なるべく生活リズムを崩さないようにサポートをしましょう。
また、子どもは学校を休んでいる後ろめたさから保護者とのコミュニケーションを避けたり、反抗的な言動をとったりすることもあるでしょう。リアクションが無かったとしても、保護者はなるべく冷静にコミュニケーションを続けましょう。あいさつや手紙でも良いです。
【不登校中期段階】特徴と正しい家での過ごし方
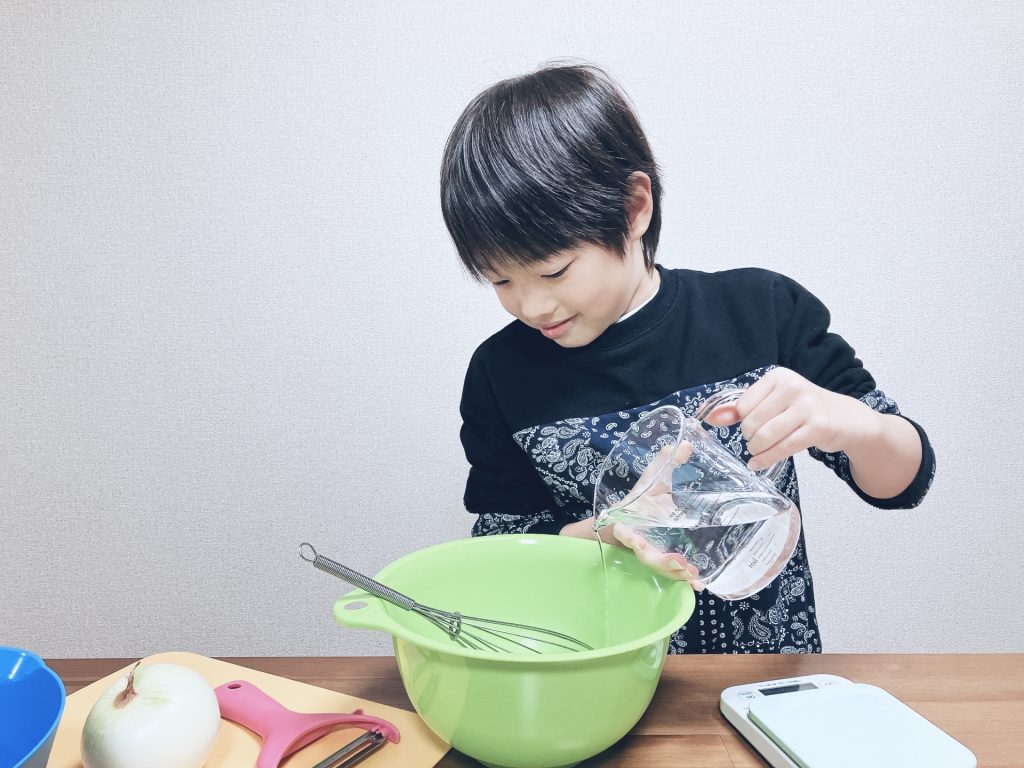
不登校中期段階は、「自分の好きな事なら出来る状態」といえます。リビングに顔を出すようになったり、ちょっと遊びに出かけたり、興味のある事なら行動できる傾向があります。
ただし、不登校は前進と後退を繰り返して回復に向かうものです。回復してきたかと思えば初期段階の状況に戻ることもあります。この時期には子どもも保護者もがんばりすぎないように注意しましょう。
以下では、小学生が家で過ごす時に気を付けたいポイントと、正しい家での過ごし方について詳しく解説していきます。
●がんばりすぎない(がんばらせすぎない)
●行動に一喜一憂しない
●親子で過ごす時間を増やすよう意識する
●成功体験を重ねるよう意識する
●家庭での役割を持たせる
●勉強を始める
まだまだ不安定な時期で、意欲的な日もあれば、何もできない日もあります。保護者が子どもの回復に一喜一憂していると、「親を喜ばせるためにがんばろう」「期待する行動をとろう」としてしまうことがあるので注意が必要です。
この時期は子どもの好きなことを一緒にやってみるなど、積極的に親子のコミュニケーションをとりましょう。親子の絆を深めることは、次のステップへの大きな一歩となるでしょう。
また、不登校の小学生には成功体験を積み重ねる機会が非常に重要です。子どもの好きなことや家庭での役割に小さな目標を設定し、それを達成することで成功を感じられるように工夫してみましょう。成功体験を通じて自信をつけ、自己肯定感を育てることが子どもの原動力となります。
自己肯定感が少しずつ回復してきたと感じたら、負担にならない程度に勉強を始めてみましょう。再登校後に授業についていけず、不登校になってしまうケースもあります。一人でいきなり勉強するのが難しかったり、塾に行くための外出が難しかったりする場合、家庭教師を利用するという方法があります。家庭教師は外出することなく授業を受けられるので、不登校の子どもには負担が少ない学習方法です。学研の家庭教師の不登校コースでは、専門の先生が勉強だけでなくメンタル面や生活面のサポートもおこないます。
【不登校後期段階】特徴と正しい家での過ごし方

不登校後期段階は、エネルギーが溜まり、「気力が外に向く状態」で、ようやく次の一歩に向けた動きが取れる段階です。
会話が増える、暇そうな時間が増える、などの傾向があります。また自分から勉強を始める場合もあります。勉強をしなくても、勉強について不安を漏らしたり、お友達の話をし始めたりした時には、「何かしたいな」「何かしなきゃな」という気持ちが隠れています。
以下では、小学生が家で過ごす時に気を付けたいポイントについて詳しく解説していきます。
●子どもの行動に過剰に反応しない
●先回りした行動をとらない
●焦らず、無理をしない
●生活環境を整える
●勉強習慣をつける
●体力をつける
●時短登校、別室登校をしてみる
●教育支援センター(適応指導教室)・フリースクールの見学をする
保護者がスムーズに学校復帰をさせたいと考えてしまう気持ちはわかりますが、復学の準備を始めることをプレッシャーに感じてしまうこともあります。子どもが自分からやりたいと思うまではそういった行動を見せることは禁物です。
子どもが学校に行く意思を見せた場合には少しずつ時短登校や別室登校から始めましょう。
復学を希望しない場合にも、教育支援センターやフリースクール、塾など、次の一歩の選択肢はたくさんあります。子どもが外とのつながりを作り、成功体験を作るサポートをすることが大切です。
同時に生活習慣をつける、外へ出て、散歩するなどして体力をつける、勉強習慣をつけるなど、次の一歩に向けたサポートを行いましょう。
まとめ
不登校の子どもの心身の状態によって、保護者が気を付けたいこと、家での正しい過ごし方を紹介しました。
どの時期にも共通することは、保護者は子どもが安心して過ごせる環境を作り、生活リズムを安定させるサポートをおこなうことが大切であるということです。こうした保護者の働きかけが、不登校の小学生にとっての正しい過ごし方に繋がるでしょう。
弊社が運営する学研の家庭教師 不登校専門コースでは、不登校支援に豊富な実績を持つ講師が対応します。お子さまの気持ちに寄り添いながら、安心できる関係性づくりを大切にしています。まずはお気軽にご相談ください。