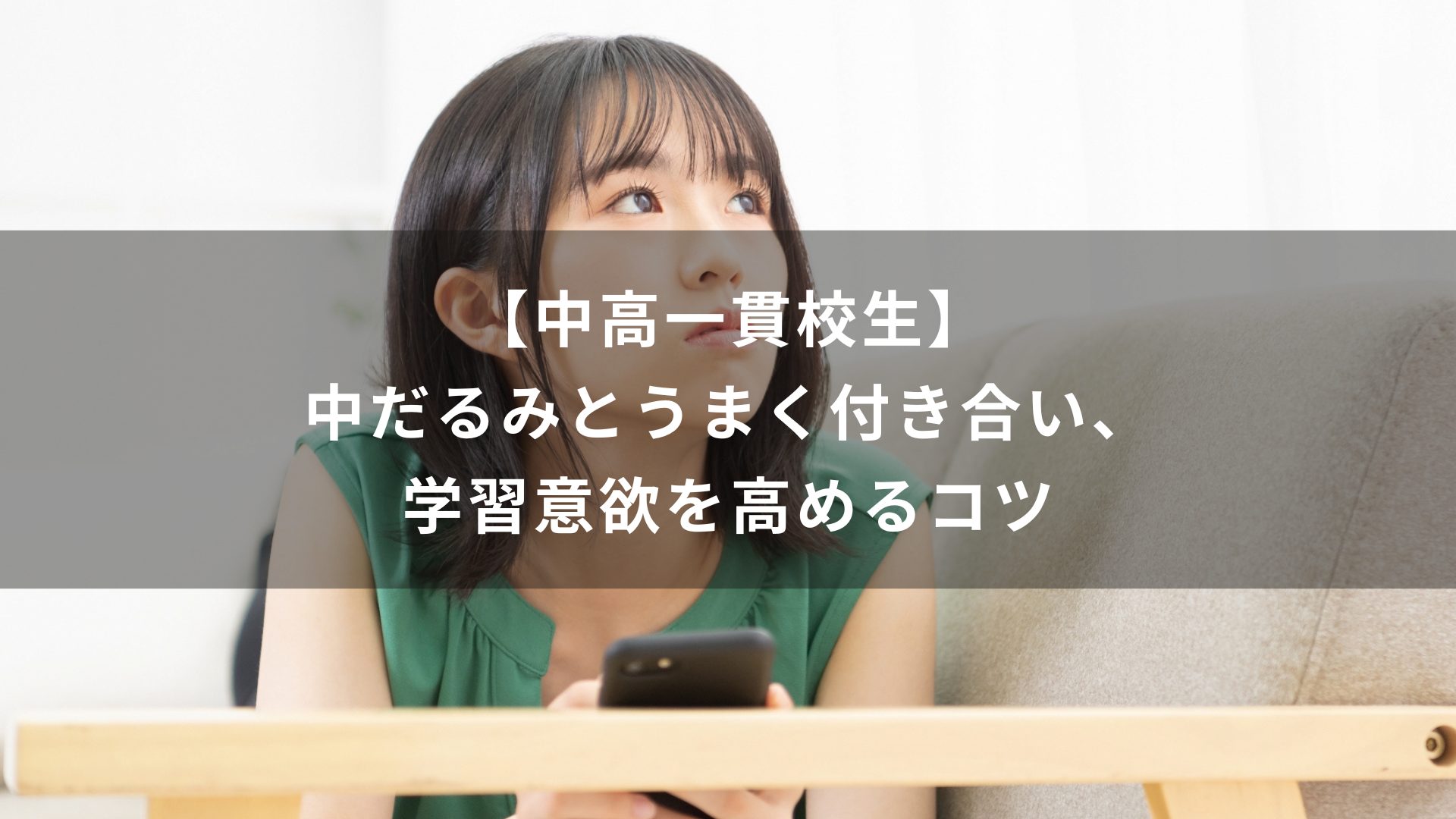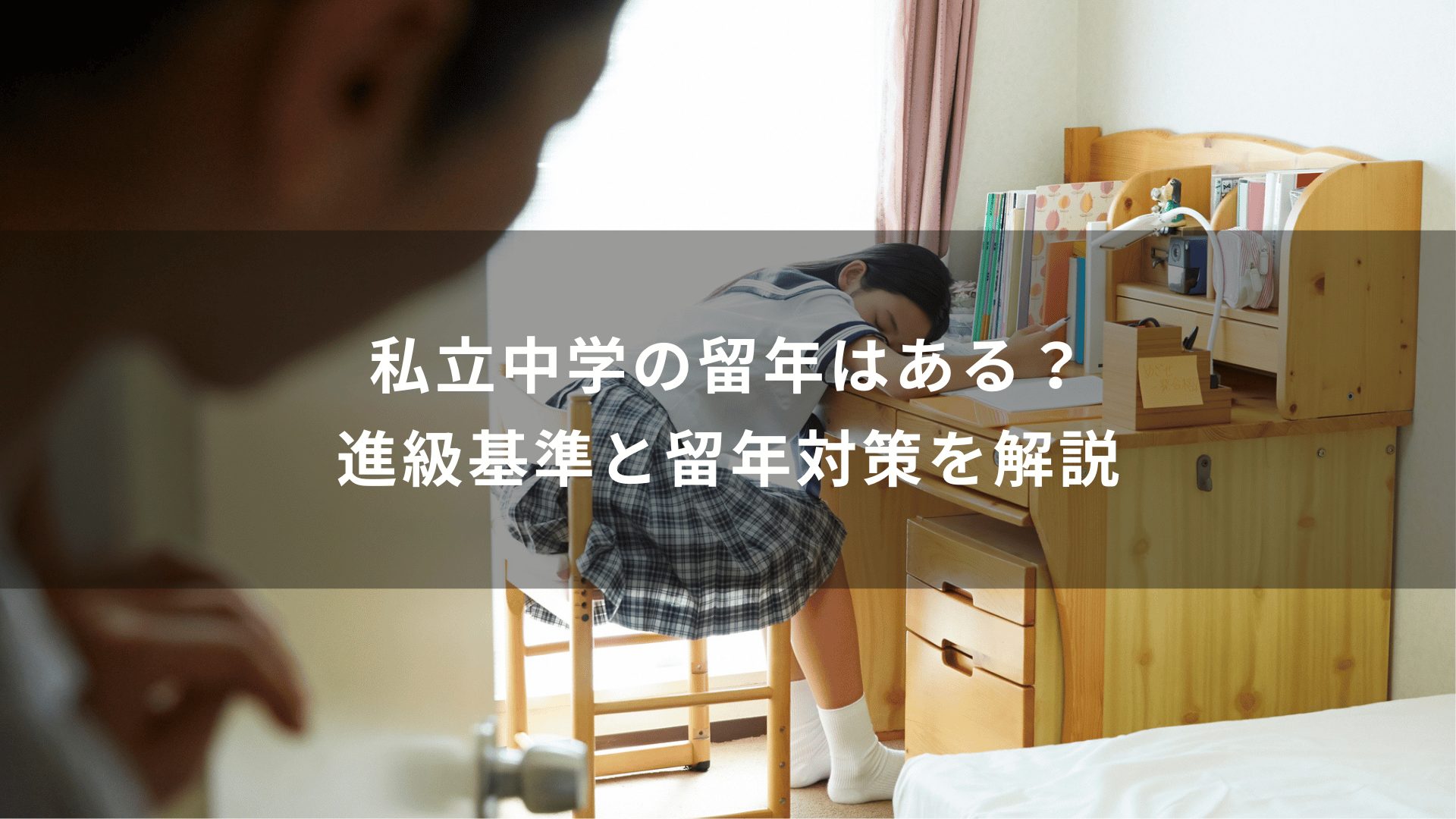中高一貫校は、6年間一貫した大学受験を視野にいれた効率的なカリキュラムを提供する環境です。しかし、その一方で、中学生の中盤あたりから高校初期にかけて「中だるみ」に悩む生徒や保護者が多いことも事実です。思春期を迎えたお子さんに対し、保護者がどのように接するべきか悩む場面も多いでしょう。
中だるみは、多くの生徒が経験する自然な現象です。ただし、適切な対処をしなければ、勉強の遅れやモチベーションの低下につながる可能性があります。
本記事では、中高一貫校生が中だるみに陥る理由や、うまく付き合いながら学習意欲を取り戻すための具体策を紹介します。
中高一貫校生が「中だるみ」を経験する理由

中高一貫校生に特有の「中だるみ」は、さまざまな要因が絡み合って起こります。ここでは、その原因を解説します。
6年間の安定した環境によるマンネリ感
中高一貫校では、6年間大きく環境が変わることはありません。新しい環境に入ったばかりの頃はやる気に満ちていても、しばらくすると学校生活に慣れて、モチベーションが下がってしまうことがあります。また、高校受験がない安心感が「まだ大丈夫」という油断に繋がり、勉強への意欲を低下させる要因となることがあります。
進度の速いカリキュラムへの対応不足
中高一貫校のカリキュラムは進度が速いため、基礎が不十分なまま次の単元に進むと、学習の理解が追いつかなくなるケースがあります。特に、数学や英語といった積み重ねの教科では、過去の内容が曖昧なままだと、次の内容に進む際につまずきやすくなります。このような状況が続くと、苦手意識やモチベーションの低下につながります。
次に目指す目標が不明確で学習意欲が低下する
中学受験という大きな目標を達成した後、「次に何を目指せばいいのか」が明確でない生徒もいます。将来の進路や夢に関する具体的な目標がないと、勉強の意義が見えにくくなり、結果としてモチベーションが低下してしまうのです。
中高一貫校生の中だるみの兆候とは

中だるみは、多くの生徒が経験する自然な現象ですが、兆候に気づかずに放置してしまうと、成績や将来の進路に大きな影響を与える可能性があります。ここでは、中だるみの兆候を見極めるためのポイントをご紹介します。
学習習慣の変化
中だるみの兆候の一つとして、学習習慣の乱れが挙げられます。以下のような状態が見られる場合、中だるみの可能性があります。
・以前は家庭学習をしていたのに、机に向かう時間が減った
・机に向かっても「なんとなくノートを開くだけ」の状況が見られる
・部活や趣味に時間を取られ、宿題や予習・復習を後回しにしている
・テスト勉強を計画的に行わず、テスト直前に焦って詰め込みをしている
親や教師との会話が減少する
中だるみが進行すると、親子間や教師との会話が減少することがあります。たとえば、勉強や進路の話題を避けたり、親の質問に反発したりする場合が多いです。さらに、学校から『授業中にぼんやりしている』といった報告を受けた際は、中だるみの可能性を検討しましょう。
中だるみが成績や進路に与える影響

中だるみは一時的な現象に思えますが、放置すると成績や進路に大きな影響を与えることがあります。ただし、中だるみの兆候を早めに察知し、適切に対応することで、挽回するチャンスは十分にあります。特に、基礎固めを徹底することで、大学受験に向けた準備を万全に整えることが可能です。ここでは、中だるみが具体的にどのような形で生徒の学習や将来に影響を及ぼすのかを解説します。
定期テストや模試の成績が低迷する
中だるみによって、日々の学習習慣が崩れると、まず目に見える形で現れるのが成績の低迷です。特に、定期テストや模試は、積み重ねが必要な教科(数学や英語)での点数の変化が顕著になりやすいです。結果から自信を喪失し、さらに勉強から遠ざかる悪循環に陥ることがあります。
受験への長期的な準備不足
中高一貫校生は、高校3年の1年間で大学受験に集中できる環境にあります。一方で、中学・高校初期の内容がしっかりと身についていないと、高校後半での学習が追いつかなくなる恐れがあります。特に、基礎固めが重要な科目では、中だるみの影響が大学受験期まで響いてしまうことがあります。
進路選択を狭める
中だるみの期間が長引くと、勉強への目的意識が薄れてしまい、進路や将来の目標が曖昧になることがあります。その結果、希望する進学先を諦めざるを得なくなる可能性もあります。早い段階で目標を再設定することが重要です。
中だるみ解消のために親ができること

中だるみを完全に解消するのは簡単ではありませんが、うまく付き合いながら少しずつ学習意欲を取り戻すことは可能です。ここでは、親の関わり方を中心に、克服と予防の両面から具体的な方法を解説します。
親は中だるみを否定せず受け入れ、味方になる
中だるみは誰にでも起こり得る現象で、大人でも仕事や趣味が「マンネリ化」してしまうことがあると思います。そんな時に否定したり叱責したりすることは逆効果です。親は「今はそういう時期なのだ」と受け入れて共感する立場であることが思春期の子供にとって大切です。
将来の進路ややりたいことを一緒に考える
将来の進路や夢に基づいた中長期的な目標を設定することも重要です。たとえば、子どもが興味を持つ分野や得意な教科に関連する進路を話し合うことで、「なぜ勉強するのか」を納得しやすくなります。保護者が一方的に決めるのではなく、子どもの意見を尊重しながら一緒に考えることで、目標に対するモチベーションが高まります。
学習目標は小さく立てる
勉強習慣を取り戻すには、短時間から始めるのがおすすめです。「今日は10分だけ英単語を覚えよう」といった目標設定で、達成感を得られるようにすると、少しずつ意欲が湧いてくることがあります。
また、多くの中高一貫校では、生徒の中だるみを防ぐために、校内イベントや、進路指導を通じて学習意欲を刺激する工夫を行っています。保護者は学校の取り組みに積極的に関わり、お子さんの状況を共有しましょう。
生活リズムを整え、学習時間を無理なく確保する
中だるみは生活習慣の乱れとも深い関係があります。早寝早起きやスマホの使用時間を見直し、無理なく勉強に取り組める環境を整えることがポイントです。子どもが睡眠不足の影響を感じることなく学習を続けられるよう工夫しましょう。
外部の力を借りて新たな刺激を与える
学校や家庭での取り組みだけでは限界がある場合、外部の教育機関を活用するのも効果的です。塾や家庭教師はもちろん、中高一貫校生専門のプログラムを提供している教育機関を利用することで、受験に向けた適切な学習方法を身につけられるでしょう
弊社が運営する学研の家庭教師では中高一貫校生専門のコースがあります。学校とは異なる視点で子どもに寄り添い、一人ひとりに合わせた指導を行うことができます。
まとめ
中高一貫校生の中だるみは、多くの生徒が経験するものです。大切なのは、保護者が子どもを否定することなく受け入れ、適切にサポートすることです。さらに、第三者の力を借りることで新たな視点や刺激を提供し、中だるみを前向きに乗り越えることができます。
本記事でご紹介したコツを取り入れ、お子さんが充実した学校生活を送れるよう、ぜひサポートしていきましょう。