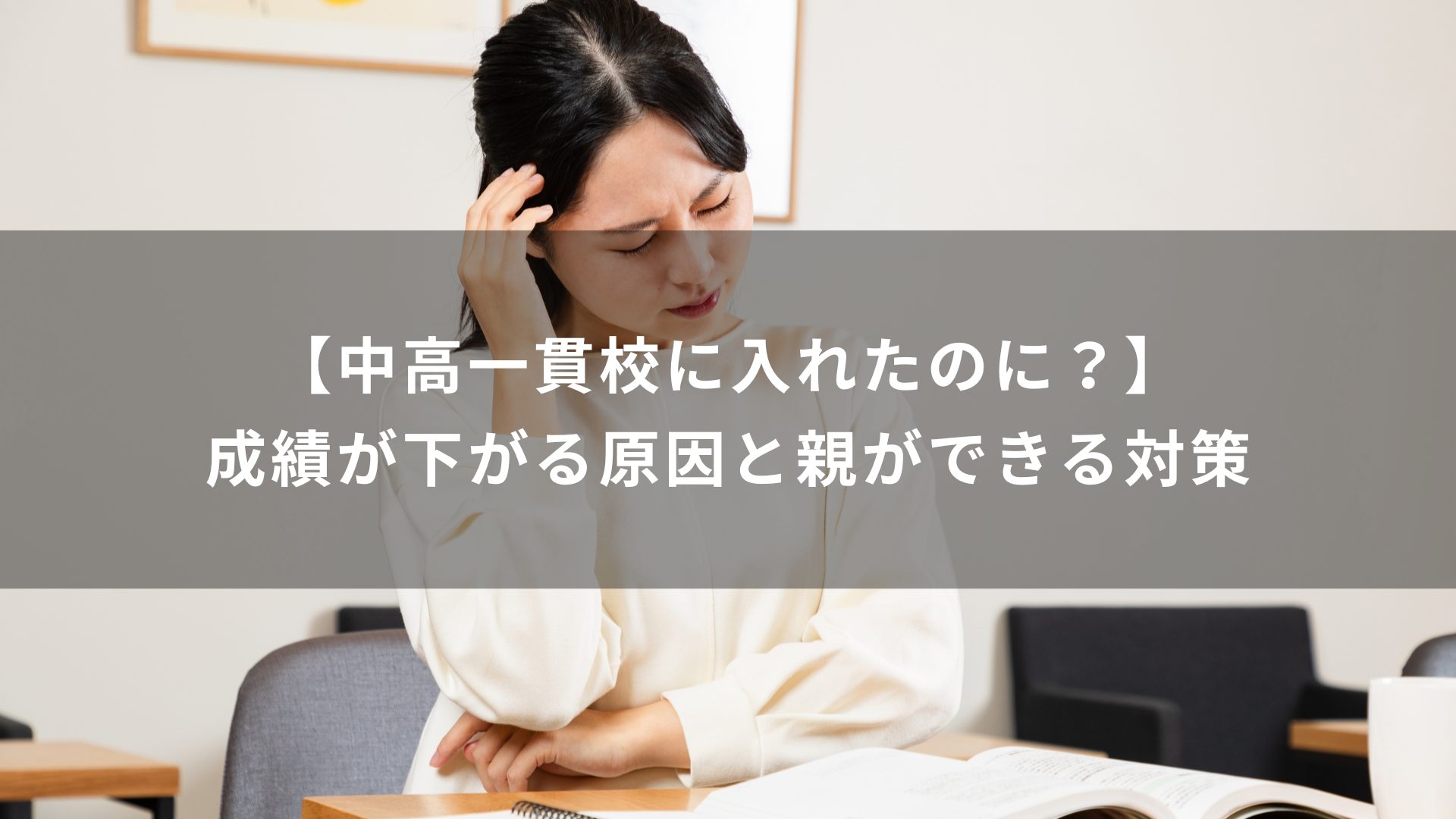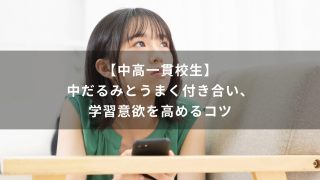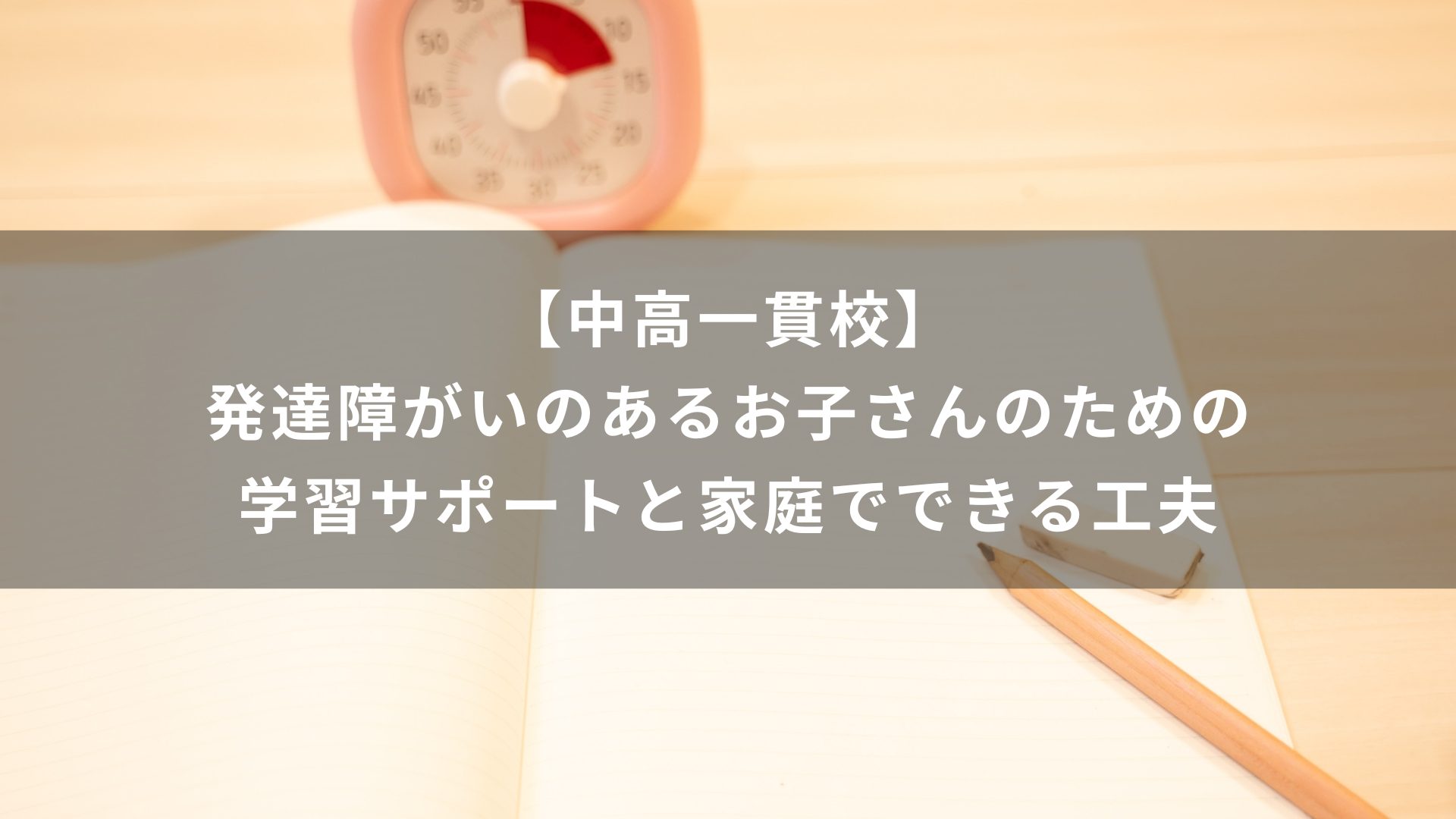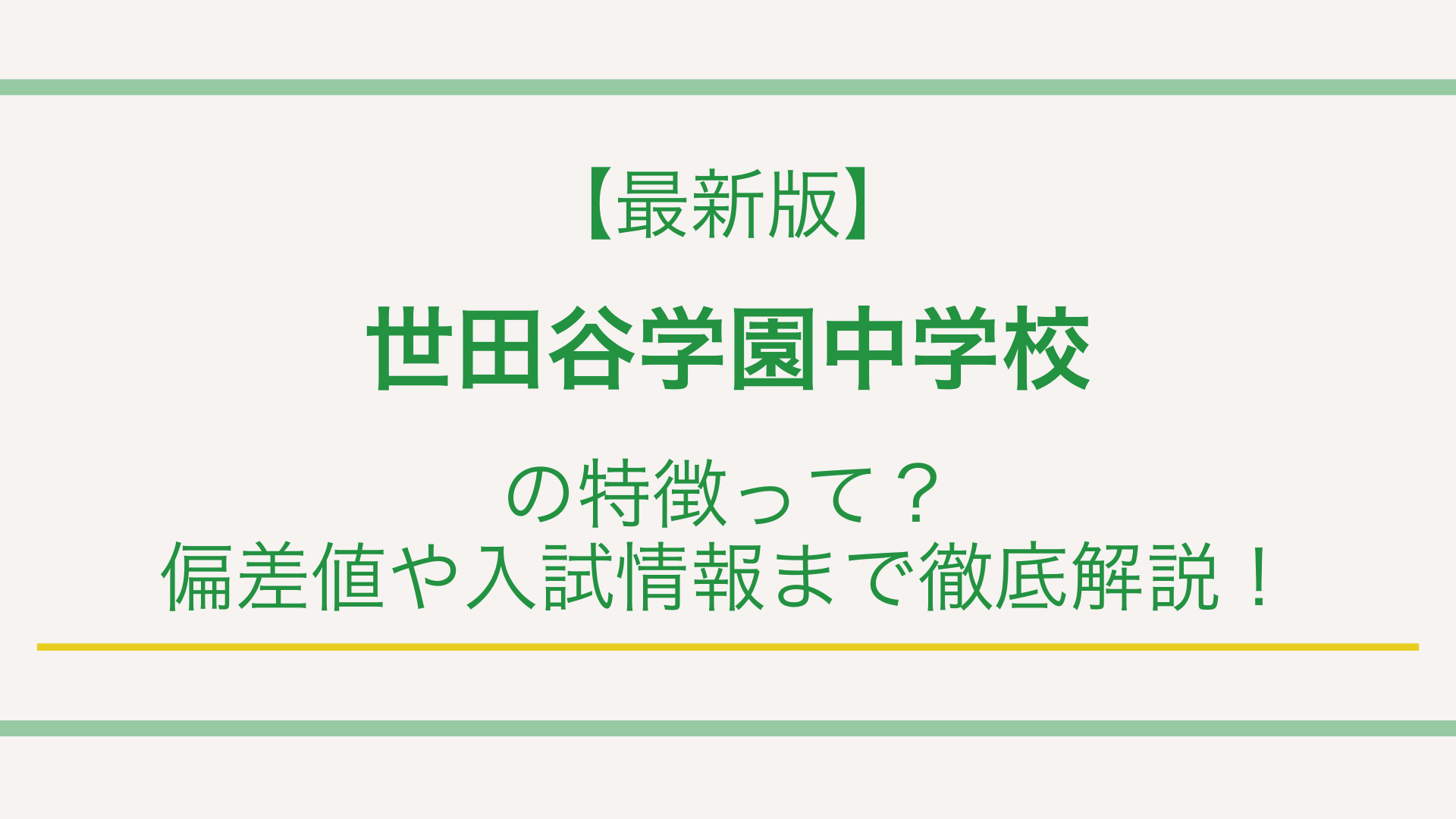中学受験を乗り越え、晴れて中高一貫校に入学。「これでひと安心」と思っていたのに、「成績が下がった」「授業についていけなくなった」という悩みを抱えていませんか?
実は、中高一貫校では受験勉強の延長では通用しない壁に直面する子どもが少なくありません。
「うちの子、大丈夫かな?」と不安を感じている方のために、本記事では以下のポイントを解説します。
・中高一貫校で成績が伸び悩む原因
・成績を上げるための対策
・放置すると起こるリスク
・家庭でのサポートが難しい場合の対処法
お子さんの学習について不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
「中高一貫校なら安心」じゃなかった?成績が下がる意外な落とし穴
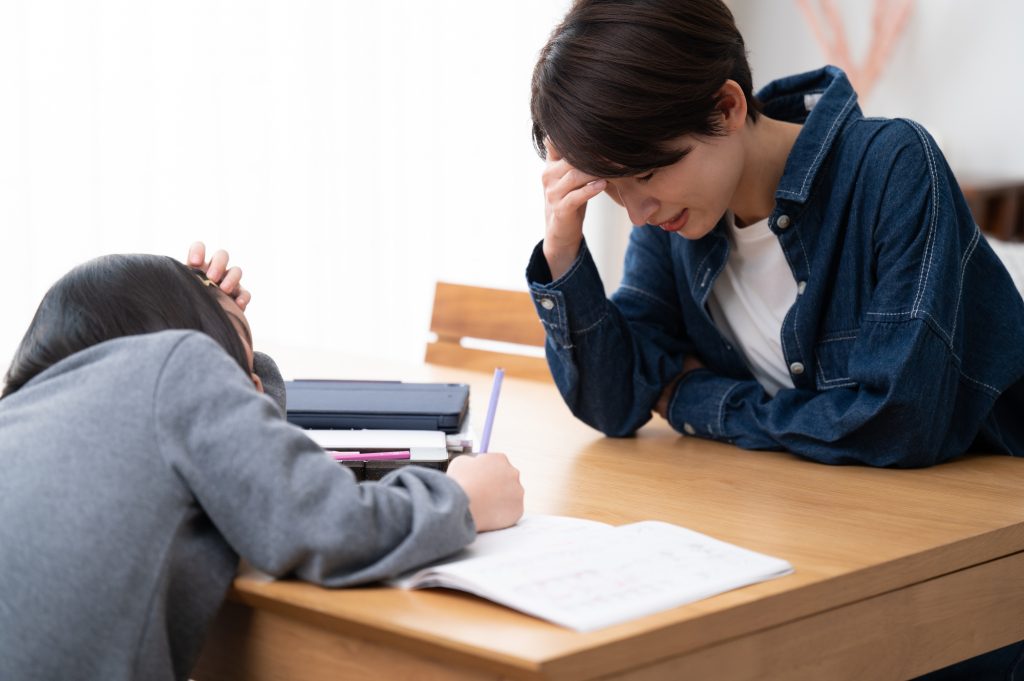
「中高一貫校に入れたのだから、もう勉強の心配はいらない」そう思っていたのに、気づけば成績が下がり、子どもが勉強に苦しんでいる…。そんな状況に戸惑っているご家庭は少なくありません。
中高一貫校の学習環境は、公立中学とは大きく異なります。授業の進度が速く、求められる学力のレベルも高いため、「受験を突破したから大丈夫」という安心感が、思わぬ落とし穴になることもあります。
では、なぜ中高一貫校に合格した子どもたちが、成績不振に陥ってしまうのでしょうか?その「意外な落とし穴」を詳しく解説していきます。
勉強不足と学習習慣の乱れ
▶よくある思い込み:「受験を乗り越えたのだから、勉強習慣は身についているはず」
➡ 実際は…「受験期と今では、求められる勉強のスタイルが違う」
中学受験では、親がスケジュールを管理し、塾や家庭教師のサポートを受けながら勉強を進めるのが一般的です。そのため、「自分で学習計画を立てる」という経験が少ないまま入学を迎える子が多いのです。
しかし、中高一貫校では、受験のときのように「やるべきこと」が明確に示されるわけではなく、学習の管理を自分で行う必要があります。
とはいえ、これまで親の手厚いサポートがあったため、「自分で勉強する方法がわからない」という状態に陥ることが少なくありません。
▶その結果…
・家庭学習の習慣が身についていない(親のサポートがなくなった途端、勉強しなくなる)
・宿題の提出が遅れたり、試験前の準備が不十分になったりする(計画的に勉強する習慣がない)
・親が介入しないと勉強しなくなる(自律的に勉強する力が育っていない)
「受験を乗り越えたのに、親が声をかけないと勉強しなくなってしまった…」 と戸惑う保護者も多いのではないでしょうか?
学校のレベルに合わず授業についていけない
▶よくある思い込み:「受験に合格したのだから、授業についていけるはず」
➡ 実際は…「中学受験の知識と、中高一貫校の授業内容は別物だった」
「受験勉強であれだけ頑張ったんだから大丈夫だろう」そう思っていたのに、授業についていけず苦しむケースは少なくありません。なぜ、授業についていけなくなるのか?それは、「受験勉強」と「中高一貫校の授業」で求められる力が異なるからです。
・限られた時間内で、正解にたどり着く計算力や処理力
・出題パターンを見抜いて、効率的に解く力
・覚えた知識を活用し、素早く正解にたどり着く力
・公式や知識を活用し、論理的に考える力
・暗記に頼らず応用する力
・仮説を立て、試行錯誤しながら答えを導き出す力
そのため、「受験に合格する力」と「授業についていく力」はイコールではありません。
・入学時にギリギリで合格した場合
→基礎が不十分なまま高度な授業に進んでしまう
・暗記中心の勉強に慣れていた場合
→パターンにない問題に対応できず、理解が追いつかない
・自分で考える習慣がない場合
→「答えがすぐに出せない」と焦り、勉強への自信を失う
「受験に受かったんだから大丈夫」と思っていたのに、まさかのつまずき…。保護者の方はもちろん、生徒自身も戸惑うことが多いポイントです。
中だるみによる学習意欲の低下
▶よくある思い込み:「高校受験がないから、のびのび勉強できるはず」
➡ 実際は…「高校受験がないからこそ、勉強しなくなる」
中高一貫校の大きな特徴の一つは、高校受験がないことです。小学生の頃は受験勉強に集中していた子どもも、「合格した」という達成感から、中学入学後に気が緩んでしまうことがあります。これがいわゆる「中だるみ」です。
・「定期テストで高得点を取る目的意識が薄れる」(受験がないため、テストの重要性を感じにくい)
・「高校受験がないことで、勉強のモチベーションを維持しにくい」(明確な目標がなくなる)
・「部活や友達との時間が増え、学習時間が減る」(勉強よりも遊びや部活を優先しがち)
「受験がないから安心」ではなく、「受験がないからこそ、勉強しなくなる」という現実に直面するご家庭も多いのです。
中高一貫校生が中だるみとうまく付き合いながら学習意欲を高めるコツを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
成績不振を放置するとどうなる?取り返しがつかなくなる前に

「中高一貫校に入れたのに」成績が低迷している…でも、今はまだ大丈夫と思っていませんか?
成績の低迷が続いているけれど、「そのうち何とかなるだろう」「中高一貫校だから最終的には高校まで行けるはず」と思って放置してしまうご家庭も少なくありません。
しかし、成績不振を放置すると、気づいたときには取り返しのつかない状況になっていることも…。ここでは、成績が低迷し続けることで起こる可能性のある問題を解説します。
内部進学に影響を与える
▶よくある思い込み:「中高一貫校なら、高校には進学できるはず」
➡ 実際は…「成績次第では、内部進学できないケースもある」
中高一貫校では、高校への内部進学が基本的に保証されているものの、一定の成績基準を満たしていないと、進学が難しくなることがあります。
・評定が一定の基準に満たないと、内部進学ができない
・進学時のクラス分けで、低成績だと厳しい環境になる(進学後の学習についていけなくなる)
中学3年生の進級時に「評定が足りない」と指摘されるケースも。高校進学時に想定外の壁にぶつかることもあります。
中高一貫校の進学基準について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
学習の遅れを取り戻すのが大変になる
▶よくある思い込み:「少しの遅れなら、後で取り戻せばいい」
➡ 実際は…「中高一貫校のカリキュラムでは、一度遅れると追いつくのが難しい」
一度つまずくと、学習内容が積み重なっているため、簡単には追いつけません。
・数学や英語など、前の単元が理解できていないと次に進めない
・復習すべき範囲が広がりすぎて、どこから手をつけていいかわからなくなる
成績が低迷しているのに放置してしまうと、いざ頑張ろうと思ったときには、すでに取り戻すのが困難という状況になりかねません。
「もっと早く対策しておけばよかった…」と後悔しないために、今すぐできることを考えましょう。
成績が伸び悩む生徒が成績を上げるための対策
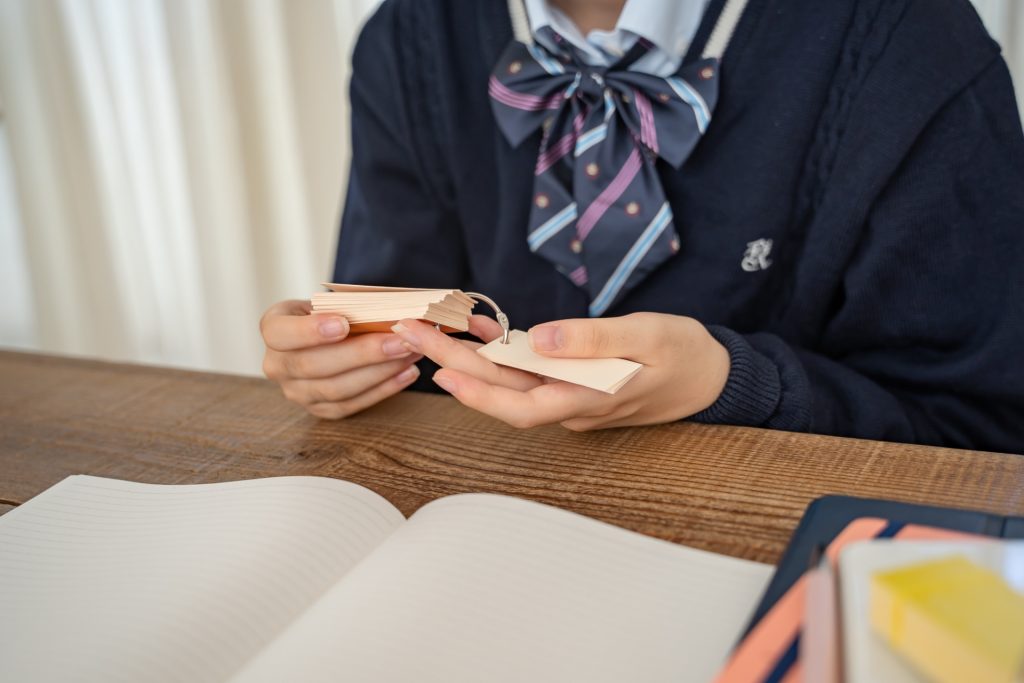
成績が下がってしまった場合、早めの対策が何より重要です。放置すると学習の遅れが積み重なり、取り返すのが難しくなるため、計画的に学習習慣を立て直すことが求められます。ここでは、成績不振の子どもが学力を向上させるための具体的な方法を紹介します。
学習習慣の見直し
学習習慣の乱れが成績低迷の大きな要因の一つです。毎日の学習リズムを整え、継続できる仕組みを作ることが重要です。
・毎日少しずつ学習を継続する
中高一貫校の勉強は一夜漬けでは効果が出にくく、日々の積み重ねが大切です。短時間でもよいので、毎日机に向かう習慣をつけましょう。
・学習環境を整える
スマホやゲームなどの誘惑を減らし、勉強に集中できる環境を作りましょう。リビングでの学習や、タイマーを使った学習法も効果的です。
・スケジュール管理を意識する
いつ・何を・どのくらい学習するのかを明確にし、学習計画を立てることが大切です。親が適度にサポートしながら、子ども自身が主体的に学習計画を考えられるように促しましょう。
基礎学力の定着
基礎が身についていないと、授業の内容が理解できず、さらなる学力低下を招く可能性があります。特に、数学や英語のような積み重ねが必要な科目は、基礎をしっかり固めることが大切です。
・数学:計算練習を繰り返す
数学の基礎力を向上させるには、計算ミスを減らすことが不可欠です。基礎的な計算問題を繰り返し解くことで、スムーズに問題を解く力を身につけましょう。
・英語:単語と文法を重点的に復習
英語は単語力と文法の理解が不可欠です。毎日コツコツと単語を覚える習慣をつけ、文法の基礎をしっかり学ぶことで、長文読解やリスニングにも対応できるようになります。
・わからないところをそのままにしない
わからない問題を放置すると、学習の遅れがどんどん広がってしまいます。疑問を感じたら、すぐに先生や家庭教師に質問し、早めに解決する習慣をつけましょう。
学習計画の立て方を工夫する
効率的に学習を進めるためには、計画的に学ぶことが重要です。闇雲に勉強するのではなく、目的意識を持って学習を進めることが、成績向上への近道になります。
・試験前だけでなく、日常的に学習を進める
テスト直前に焦って詰め込むのではなく、日々の授業で習った内容を復習しながら学習を進めることが重要です。
・1週間単位で学習計画を立て、進捗を確認する
1日の計画ではなく、1週間単位でスケジュールを作成すると、柔軟に調整しながら勉強を進めることができます。例えば、月曜に数学、火曜に英語といった形で科目ごとにバランスよく学習を進めると、効率的に学べます。
・優先順位をつけて学習に取り組む
すべての科目を同じように勉強するのではなく、苦手な分野を重点的に学習することで、効率よく成績を向上させることができます。
成績が低迷した際には、焦らず基本に立ち返り、計画的に学習を進めることが大切です。家庭でのサポートと合わせて、子どもが主体的に勉強できる環境を整えていきましょう。
家庭だけではどうにもならない場合は外部のサポートを取り入れよう
成績が低迷し、家庭でのサポートだけでは対応しきれない場合、外部のサポートを活用することも選択肢の一つです。子どもが「何をどう勉強すればいいのかわからない」「授業についていけない」と感じているなら、専門的な指導を取り入れることで学習の遅れを取り戻し、自信を回復させることができます。
プロの指導を受けるメリット
家庭での学習サポートには限界があるため、専門的な知識を持つプロの指導を受けることで、効率よく学力を伸ばすことが可能です。
・第三者の指導のほうが効果的
親が勉強を教えようとしても、感情的になったり、適切な指導方法がわからなかったりすることがあります。家庭教師や塾の講師などの第三者が指導することで、親子関係を良好に保ちながら学習を進められます。
・個別指導なら、苦手な分野を重点的にサポートできる
一斉授業ではなく、マンツーマンや少人数指導を取り入れることで、子どもがつまずいている部分を集中的にフォローできます。特に、中高一貫校の進度に対応した指導が受けられるサービスを活用すると、より効果的に学習の遅れを取り戻せます。
・モチベーションの維持につながる
一人で勉強するのが苦手な子どもも、講師と一緒に学習することで、学習への意欲を保ちやすくなります。プロの指導を受けることで「できる!」という成功体験が増え、勉強への自信がついてくるでしょう。
学研の家庭教師の中高一貫校生コースのご紹介
「授業についていけない」「学習の進め方がわからない」といったお悩みをお持ちの方へ、
学研の家庭教師では、中高一貫校の生徒向けに特化した指導を行っています。
・中高一貫校のカリキュラムに合わせた指導
中高一貫校では、学校ごとに独自の進度や教材が採用されているため、一般的な学習サポートでは対応が難しい場合があります。学研の家庭教師では、お子さんの通う学校のカリキュラムに合わせた指導を行い、授業の理解を深めるお手伝いをします。
・一人ひとりに合わせたオーダーメイド指導
得意科目はさらに伸ばし、苦手科目は基礎から丁寧に復習するなど、お子さんの状況に応じた指導プランを作成します。勉強が苦手なお子さんでも、無理なく学習に取り組めるように指導を進めます。
・学習習慣の定着をサポート
ただ教えるだけでなく、学習計画の立て方や勉強の仕方も指導し、自主的に学習に取り組めるようサポートします。定期的な学習習慣を身につけることで、成績向上につなげます。
学習の遅れを感じたら、早めの対策が何より大切です。学研の家庭教師を活用して、成績アップを目指しましょう。ご興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
中学受験を終え、中高一貫校に入学すれば安心と思っていたのに、成績が下がった、授業についていけないなどの悩みを抱える家庭は少なくありません。
その原因は、受験勉強と中高一貫校の学習スタイルの違いにあります。暗記中心の勉強に慣れていた子や、親のサポートのもとで勉強していた子は、自分で学習計画を立てる力が育っておらず、授業の進度についていけなくなることも。さらに、高校受験がないことで学習意欲が低下する「中だるみ」のリスクもあります。
こうした状況を放置すると、内部進学が難しくなったり、学習の遅れが取り戻せなくなったりする可能性があります。しかし、学習習慣の見直しや基礎固め、計画的な勉強を実践すれば、成績は十分に回復できます。
大切なのは、「そのうち何とかなる」と先延ばしにせず、早めに対策をとること。子どもの学習状況を見直し、必要に応じて外部のサポートも活用しながら、確かな学力を身につける環境を整えていきましょう。