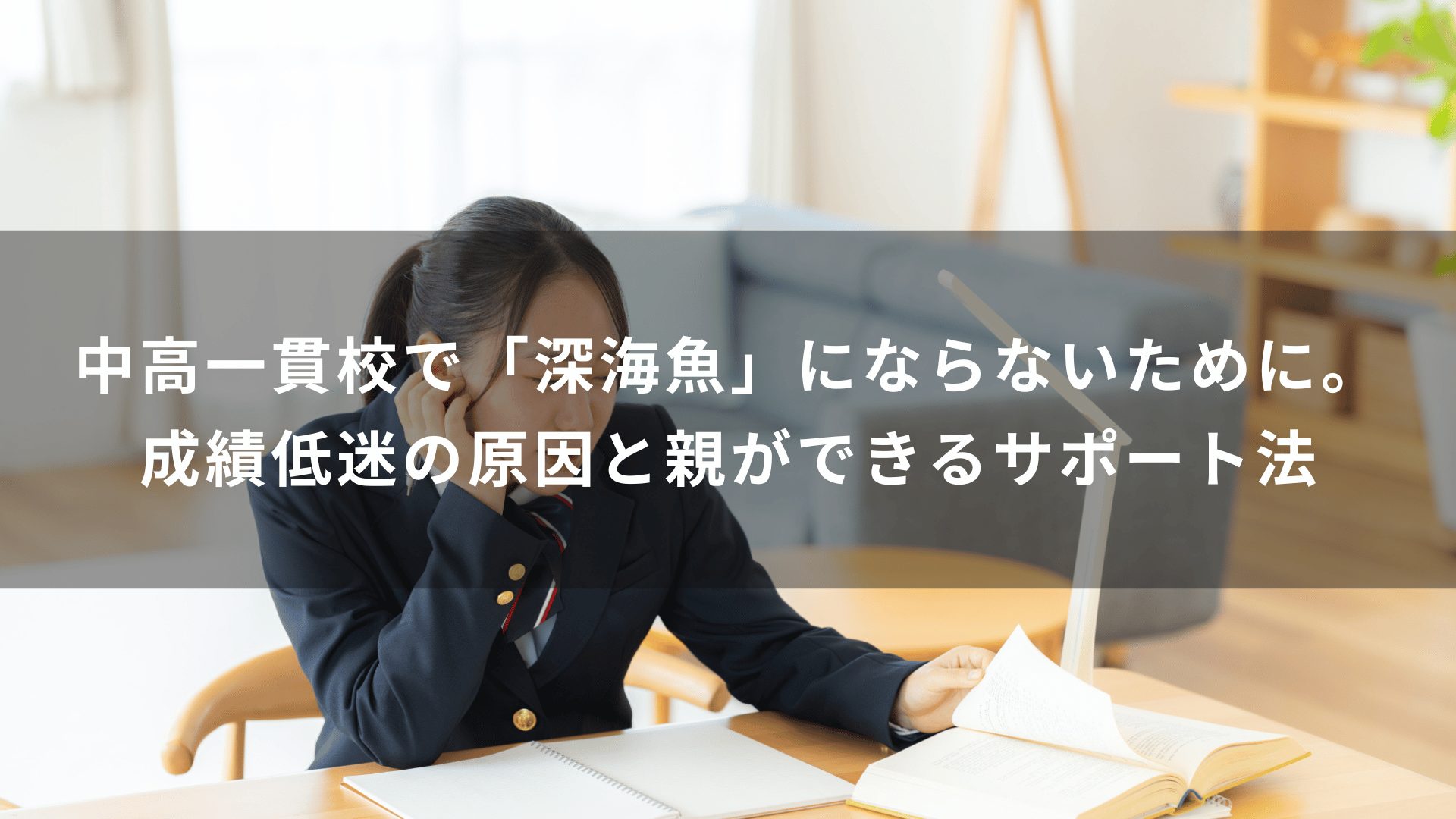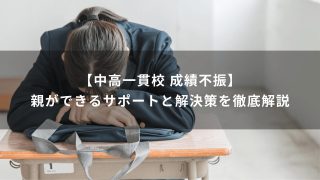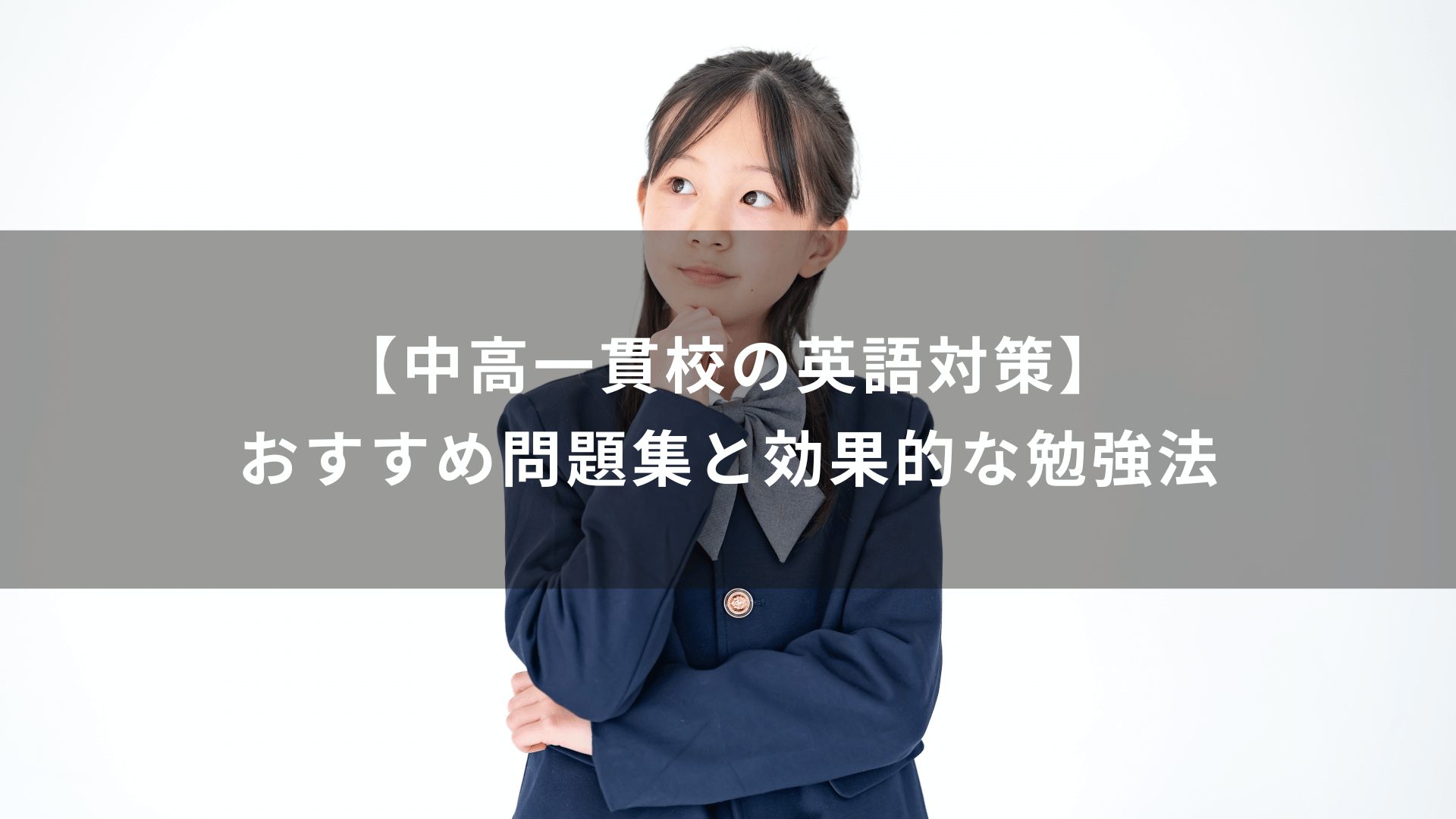「中高一貫校に入ったのに、成績がみるみる下がっている…」
「通知表を見てショックを受けたけれど、本人は何も話してくれない」
そんな不安を感じている保護者の方へ。
中高一貫校、特に私立中学では、学力の高い生徒が集まるため、入学後に成績が伸び悩むケースも少なくありません。
そうした中で、成績が下位に落ち着き、自信を失ってしまった生徒のことを「深海魚」と呼ぶことがあります。「もしかして、うちの子も…?」と感じたときに、どう受け止め、どう関わればよいのか。
この記事では、成績低迷の背景と、保護者ができるサポートについてお伝えします。
深海魚とは?中高一貫校でこの言葉が使われる理由

中高一貫校では、学力の高い生徒が多く集まり、授業の進度や難易度も高めです。
その中で、これまで「勉強が得意」と感じていたお子さんが、急に授業についていけなくなることも少なくありません。
最近では、そうした状況に陥った生徒のことを「深海魚」と呼ぶことがあります。
成績が下がりはじめ、自信を失い、学習への意欲が見えにくくなる状態を表す言葉です。
では、なぜ子どもが「深海魚」と言われる状態に陥ってしまうのでしょうか?その背景を見ていきましょう。
なぜ「深海魚」になってしまうのか?主な4つの要因

成績が下がってしまうきっかけは、お子さんの性格や学校の雰囲気によってさまざまです。
一見「やる気がないように見える」場合でも、実はその背景には戸惑いや焦り、プライドや不安といった感情が隠れていることもあります。
ここでは、実際によく見られる4つの背景についてご紹介します。
入学後の安心感から、気持ちがゆるむ
中学受験という大きな壁を乗り越えたあと、お子さんの中には「しばらくはのんびりできる」と思ってしまう子もいます。
実際、入学直後は環境にも人間関係にも慣れるのに精一杯。勉強への集中力が切れたまま、気づいたときには周りとの学力差が広がっていた、という声もよく聞かれます。
「そのうち何とかなるだろう」と本人が思っているうちは、成績が下がっていても危機感を抱きにくいもの。
そのままペースを取り戻せず、流されてしまうケースが少なくありません。
プライドが邪魔して、成績と向き合えない
「自分はもっとできるはずなのに」「こんなはずじゃないのに」
そう感じたとき、理想と現実のギャップに向き合うのがつらくなり、見て見ぬふりをしたくなることがあります。
なかには、「どうせ頑張っても無理」「周りは頭がいいから仕方ない」と、自分を納得させてしまうお子さんもいます。
本音では悔しいと感じていても、それを隠すように「別にいいし」「どうでもいい」と無関心を装ってしまうこともあるのです。
「やりたい気持ちはあるけど、やり方がわからない」
「なんとなくやる気はあるんだけど、勉強ってどうすればいいのかわからない」
これは中高一貫校のお子さんによく見られる特徴です。
中学受験までは、先生や保護者に言われたことをこなせば良かったかもしれません。
しかし中高一貫校に進学後は「自分で考えて計画を立てる力」や「主体的に学ぶ姿勢」が求められます。
その変化にうまく対応できないまま、結果が出ずにモチベーションを失っていくケースも少なくありません。
「わからない」と言えず、つまずきをため込んでしまう
「こんなこと、今さら聞いたら恥ずかしい」
「クラスメイトはできているのに、自分だけわからないなんて言えない」
このような気持ちから、授業でわからないことがあっても、そのままにしてしまうお子さんもいます。はじめは小さなつまずきでも、時間がたつにつれて大きな壁になり、やがて授業そのものが苦痛になってしまうこともあります。
特に、先生に質問するのが苦手なタイプや、人に弱みを見せたくないタイプのお子さんは、表面上は平気に見えても、実は困っているケースもあります。 こうした変化に早めに気づくことで、適切なサポートにつながります。
もしかして深海魚かも…そう感じたとき、親ができる関わり方とは?

「テストの結果が、下から数えたほうが早かった…」
「通知表を見て、想像以上に悪くてショックだった」
このような不安から、この記事にたどり着いた方もいるかもしれません。
中高一貫校では、同じように優秀だった子たちが集まっている分、想像以上に差がつくこともあります。
こんなサインが見えたら注意
「成績がかなりまずい…」と最初に気づくのは、テストの点数や通知表など、目に見える成績かもしれません。ですが、成績以外にも予兆が現れることがあります。
たとえばこんな変化、思い当たることはありませんか?
・学校の話をしなくなった、反応が淡白になった
・スマホやゲームの時間が増え、机に向かう時間が減った
・「どうでもいい」「別に」などの口ぐせが増えた
こうしたちょっとした変化は、「勉強に対する気持ち」が揺らいでいるサインかもしれません。本人が何も言わなくても、親が変化に気づき、そっと関わってくれることが、再スタートのきっかけになることもあります。
大切なのは、「見守るだけ」ではなく、「どう関わるか」。小さな変化を見逃さず、まずはできることから寄り添ってみましょう。
「どう声をかけるか」が、お子さんの心を開くカギに
成績の低下に驚いて、「なんでこんな点数なの?」「ちゃんと勉強してたの?」と問いただしたくなる気持ちは、親として自然な反応です。ですが、それがプレッシャーになってしまい、子どもがさらに心を閉ざしてしまうこともあります。
子どもへの声掛けの際は、まず保護者自身の感情ではなく、お子さんの「今の状況」に寄り添う言葉をかけてみましょう。
「どうしてこんな点数なの?」(責めているように聞こえる)
「ちゃんとやったの?」(信じてもらえていないと感じる)
「また頑張ろうよ!」(励ましのつもりでも、プレッシャーに)
「最近ちょっと疲れてる?」
「何か困ってることある?」
「どこから手をつけたらいいか、一緒に考えてみようか」
「焦らなくて大丈夫。ゆっくりでもいいから動いていこう」
声かけのポイントは、「正論」ではなく「共感」から始めること。子どもが安心して気持ちを話せるような雰囲気づくりが、再スタートのきっかけになります。
「本人が勉強を嫌がっていて、どうにも動けない…」という方は、家庭での関わり方やサポートの工夫について、こちらの記事も参考になります。
親がすべてを抱え込まなくていい。頼れる人を一緒に探す
どんなに親が頑張っても、言葉が届きにくいと感じるときもあると思います。
そんなときは、外部の力を借りることも前向きな選択肢です。
お子さんが「この人なら話せるかも」と感じるような指導者に出会えると、そこから前向きな流れが生まれてくることもあります。
弊社が運営する学研の家庭教師では、ご家庭のご希望を丁寧にヒアリングし、お子さんの性格や状況に合った先生をご紹介しています。
「先生との相性が不安」「子どもが乗り気じゃない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。また、中高一貫校専門コースもご用意しており、学校のカリキュラムや教材に合わせた指導が可能です。
まとめ
中高一貫校に通うお子さんの中には、思うように成績が伸びず、学習意欲を失ってしまうケースもあります。いわゆる「深海魚」と呼ばれる状態は、誰にでも起こり得るものです。
大切なのは、
・成績や態度の変化を早めにキャッチすること
・頭ごなしに叱るのではなく、今の状況を冷静に把握すること
・必要に応じて、家庭外のサポートも検討すること
焦らず状況を整理し、今できることから一つずつ取り組んでいくことが、成績回復への近道となります。