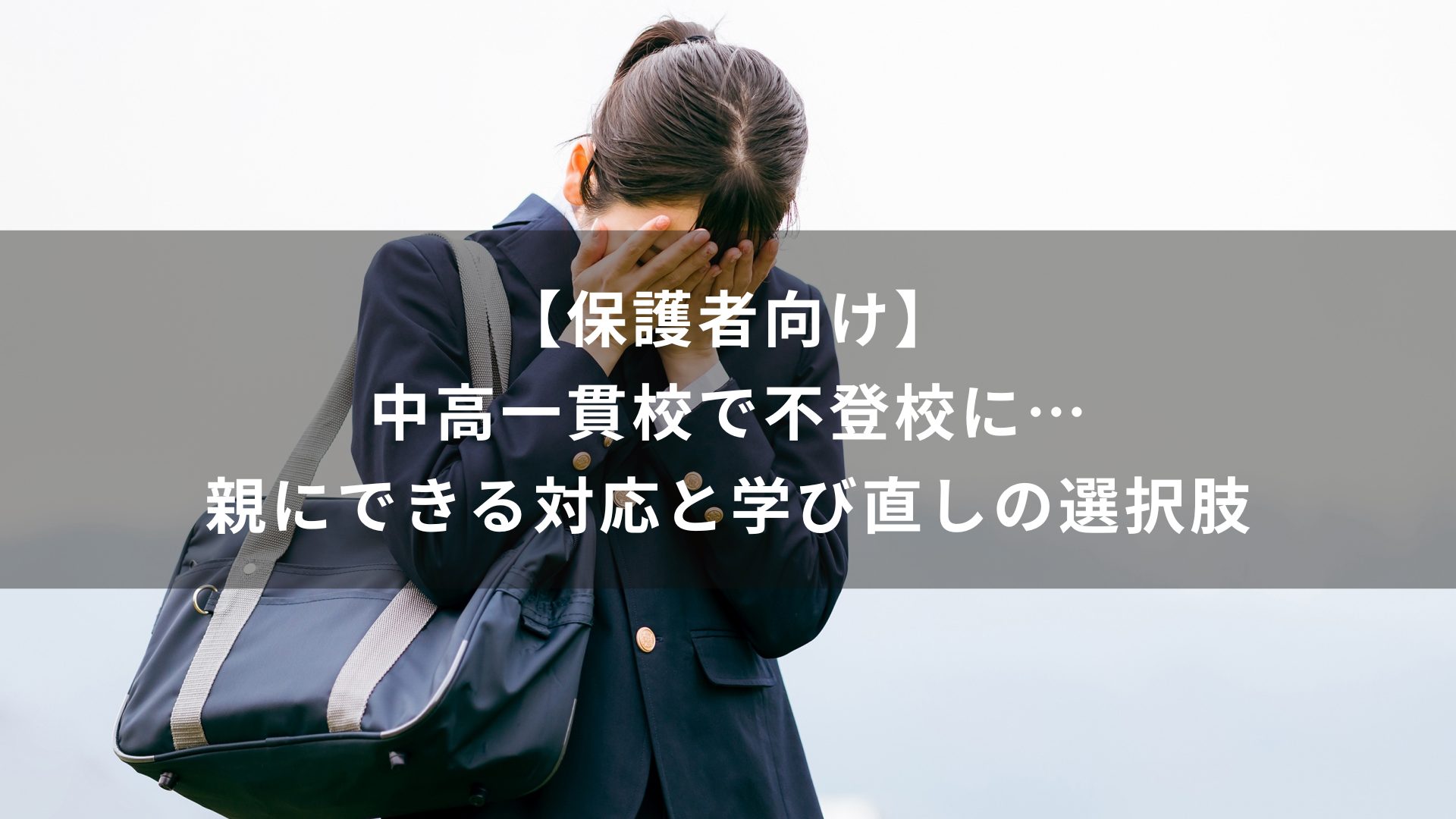中学受験を乗り越え、やっと手にしたはずの中高一貫校での生活。
けれど、期待や安心とは裏腹に、登校しづらくなったり、学校とのミスマッチに悩む子どもも少なくありません。
本記事では、
・中高一貫校生が不登校になる理由
・保護者ができること
・勉強が止まってしまったときの再スタートのヒント
・学校に戻る以外の学びや進路の選択肢
…など、不登校の今だからこそ知っておきたいことを、保護者の視点からお伝えします。
「この先どうしたらいいんだろう?」という不安を、少しでも軽くできるように。焦らず、一緒に考えていきましょう。
なぜ?中高一貫校で不登校になる子が増えている理由

中高一貫校は、受験を乗り越えて手にした“特別な場所”。
だからこそ、「まさかうちの子が…」と戸惑う保護者の方も少なくありません。
でも、実際には不登校になる子どもは決して少なくなく、その背景にはいくつかの共通する要因があります。
まずは、その理由を知ることから始めてみましょう。
中学受験を頑張った反動と燃え尽き
小学生時代に大きな努力を重ね、中学受験を乗り越えてきた子どもたち。
入学し、「目標を達成した安心感」とともに、心のエネルギーが切れてしまう“燃え尽き”状態に陥ることがあります。
特に真面目で頑張り屋の子ほど、気を張って努力し続けた反動が出やすく、
「入学したら急に無気力になった」「やる気が出ない」と感じるケースも多いです。
これは心身が休息を求めているサインで、決して怠けているわけではありません。
人間関係・環境のギャップ
中高一貫校では、多くの生徒が受験を経て集まってくるため、自然とクラスの学力レベルも高くなります。
その中で、小学校時代には「勉強が得意な子」として過ごしていた子が、「自分よりできる子がたくさんいる」と気づき、自信をなくし、自己肯定感が下がってしまうことがあります。
また、中高一貫校は6年間同じメンバーで過ごすケースが多く、人間関係が固定化しやすいという一面もあります。友人や先生との相性が合わないと感じても、環境を変えにくいことで悩んでしまう生徒もいます。
授業スピードや“先取り学習”に合わず、つまずくケースも
中高一貫校では、6年間を通した独自のカリキュラムを導入している学校が多く、高校受験を挟まないぶん、授業の進度が速くなる傾向があります。
“先取り型”の学習や、難易度の高い課題が続くことで、学びのペースに戸惑いを感じる子も少なくありません。
「周りはどんどん先に進んでいるのに、自分だけわからない気がする」
「質問しづらくて、そのまま置いていかれそう」
そんな不安が少しずつ積み重なり、やがて勉強が苦手になった、と自信をなくしてしまうこともあります。
また、高校受験がないことは中高一貫校の大きなメリットですが、裏を返せば、短期的な目標を見失いやすいという側面もあります。
「なんのために勉強しているのかわからない」「どうしても気が緩んでしまう」といった“中だるみ”のような状態は、思春期の不安定さと重なることで、学習意欲や登校意欲の低下につながってしまうケースもあるのです。
保護者として、まずできること

子どもが学校に行けなくなると、保護者としては「何とかしなきゃ」「早く登校させなきゃ」と、気持ちが焦ってしまうものです。
けれど、まず大切なのは「今、子どもがどう感じているか」に目を向けることです。
子どもの回復には、安心出来る環境で心を落ち着ける時間を作ることが最優先です。
ここでは、今すぐにできる「親としての関わり方」のヒントを紹介します。
“登校させる”ではなく“整える”
無理に登校を促すことは、逆効果になる場合があります。これは、お子さんを学校に戻したいという親心が裏目に出てしまう典型的なパターンです。
「将来に響いてしまうのでは…?」と不安になるのは当然ですが、登校を強く勧めたり、説得しようとしたりすると、子どもはさらに心を閉ざしてしまう可能性があります。
大切なのは、子どもが今、何を感じているかに寄り添うこと。「学校に行かなくても、ちゃんと見てくれている」という安心感が、心を落ち着ける第一歩になります。
また、保護者自身が必要な情報を知っておくことも、冷静に対応するための助けになります。
学校の対応方針や支援制度、今後の選択肢をあらかじめ整理しておくことで、「これからどう動けばいいか」の見通しが立ちやすくなります。
👉 行き渋りに悩む保護者必見!子どもへの適切な対応方法と頼れる相談先とは では、不登校の初期段階で見逃してはいけないサインや、避けた方がよい対応、頼れる相談先まで具体的に紹介しています。こちらも参考にしてください。
第三者の相談窓口・支援機関を知っておく
不登校の対応は、家庭だけで抱え込まず、専門的な知識や経験を持つ人に早めに相談することが回復への近道です。
なぜなら、不登校の子どもへの対応方法やタイミングによって、回復のスピードが大きく変わってくるからです。相談することに抵抗がある方もいるかもしれませんが、 「一緒に考えてくれる大人がいる」ことは、親子にとって大きな支えになります。
代表的な相談先に下記があります
・スクールカウンセラー
・教育相談センター(地域の適応指導教室)
・フリースクールやNPO団体
・不登校専門の家庭教師やオンラインスクール
「どこに相談したらいいかわからない」と感じたときには、不登校の相談先について知りたい方必見!相談先と事例をご紹介の記事内で、相談機関リストや保護者の体験談、専門家に相談するメリットなどを紹介しています。ぜひ参考にしてください。
止まってしまった勉強、どう再開すればいい?
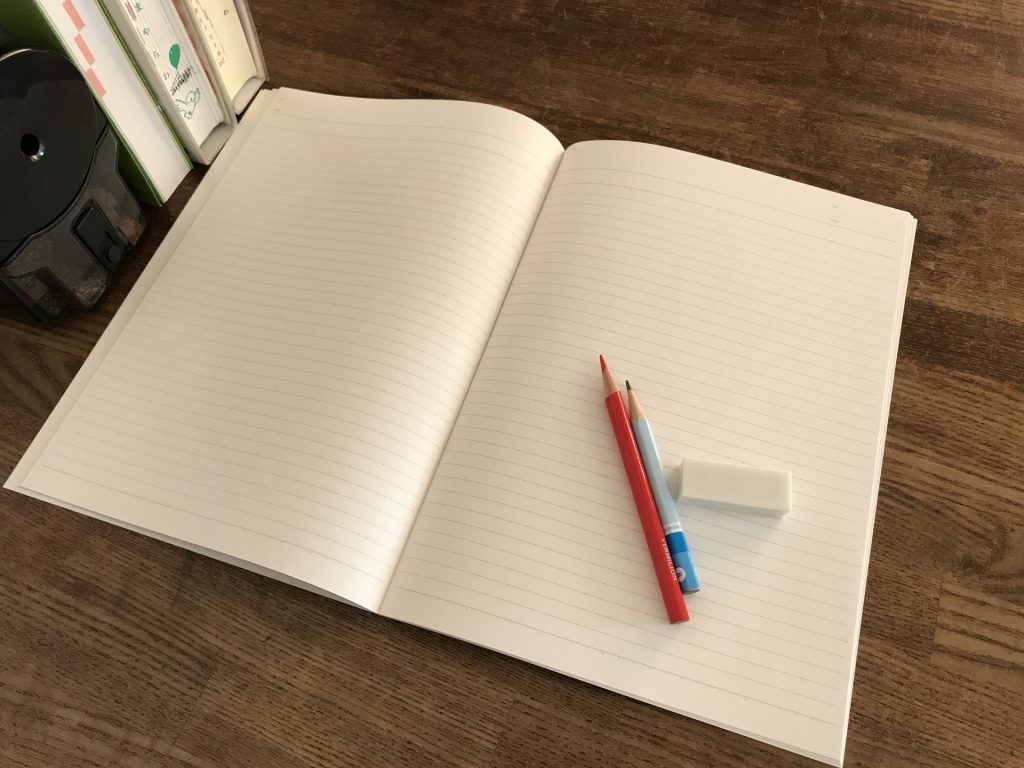
今は、必ずしも「学校に戻る」ことだけがゴールではありません。不登校の期間が続くと、「このまま勉強が遅れてしまうのでは…」と不安に感じる保護者の方も多いと思います。
けれど、焦って無理に再開しようとするよりも、子どもの状態に合わせて“今できること”から始めることが大切です。
このセクションでは、中高一貫校で不登校になったお子さんが“学び直し”に向かう際のタイミングや方法、進路の選択肢までをご紹介します。
再開のタイミングは「エネルギーが戻ってきた頃」
勉強が止まっている期間に、「そろそろ始めないと…」と感じることもあるかもしれません。
でも、エネルギーがまだ溜まっていない状態で無理に勉強を始めると、“やらされている”という気持ちだけが残ってしまい、逆効果になることもあります。
では、どんなときが再開のサインなのでしょうか。
・日中に笑顔が増えてきた
・家族との会話が増えた
・ゲームやスマホ以外のことにも興味を示した
・退屈そうにしている時間が増えてきた
こうした変化が見られる頃は、少しずつ「外に目を向ける余裕」が出てきた証拠。
最初は、1日5分の計算や漢字練習、好きな教科の動画を見るだけでもOKです。
家庭学習で“続けられる形”を見つける
家庭学習を無理なく続けるためには、次のような工夫が効果的です。
・「いつ」「どこで」勉強するかを決めておく(例:夕食前に10分)
・子どもが興味を持てる教材を選ぶ(アプリ・YouTube教材など)
・教えるのではなく、見守る・一緒にやるスタンスで寄り添う
不登校に理解のある家庭教師や、不登校専門の塾・オンライン学習サービスもあります。
「家庭では難しいかも」と感じたら、外部の力を借りることも前向きな選択です。
たとえば、弊社が運営する学研の家庭教師では、不登校の状況に特化した「学研の家庭教師不登校専門コース」に加え、中高一貫校生向けの「学研の家庭教師中高一貫校コース」もご用意しています。
お子様の現在の状況や学習の様子に応じて、最適なコースをご提案することが可能です。学力面だけでなく、「自分をわかってくれる」大人の存在が安心感につながります。
子どもに合った“学びのかたち”を一緒に探す
勉強を再開するとき、今の学校に戻ることだけが選択肢ではありません。
子どもが「安心して学べる場所」。そして、「続けやすい方法」を選ぶことが大切です。
たとえば、こんな選択肢があります。
フリースクールに通う
個別対応や自由なカリキュラムのもと、落ち着いて過ごせる居場所です。
在籍校や公立校への転校後も、出席扱いになることがあります(校長判断)。
オンラインスクールで自宅学習
映像やライブ授業を通じて、自宅でも自分のペースで学べます。
公立中学校へ転校する
学区内の学校へ移ることで、環境を変えリスタートを図ることができます。
通信制高校へ転校する
登校日数を調整しながら、自分のペースで学習を進められます。サポート校と併用するスタイルもあります。
定時制・単位制高校へ転校する
柔軟な時間割で、自分に合った生活リズムに合わせて学べます。
高卒認定を取得し、自分のペースで進学を目指す
高校卒業と同等の資格を得て、大学や専門学校への進学が可能です。
不登校専門コースのある家庭教師・塾を活用する
子どものペースに寄り添った学びの支援が受けられます。信頼できる大人の存在が、心の安心にもつながります。
子どもに合った学び方は一人ひとり違います。「再登校すること」だけにとらわれず、その子らしく学べる方法を一緒に探すことが、再出発の一歩になります。
まとめ
子どもが学校に行けなくなることは、保護者にとっても大きな戸惑いと不安を伴う出来事です。
「このままで大丈夫なのだろうか」と悩むのは当然のこと。でも、不登校は“今の状態を立て直すための時間”と捉えることもできます。
保護者として意識しておきたいのは、
・子どももまた、表には出さずとも葛藤していること
・家庭が「安心できる居場所」であり続けることの大切さ
・“学校に戻る”ことより、“心を整える”ことに目を向けること
・必要なときには周囲の支援を頼っていいということ
焦る必要はありません。大切なのは、「今できること」から、少しずつ進んでいくこと。子どもにとって安心できる居場所があるだけで、少しずつエネルギーを取り戻し、前に進む力を蓄えていきます。
保護者の方も一人で抱え込まず、周囲の力や情報を頼りながら、親子で歩んでいきましょう。